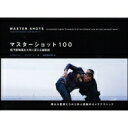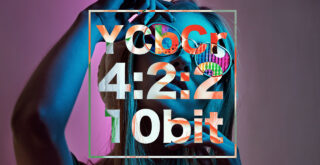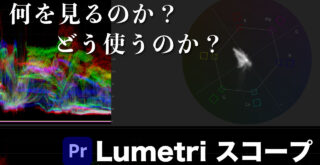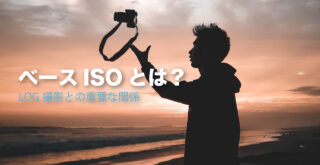独学で映像クリエイターを目指していると、作品作りのアイデアに詰って苦しい思いしたりしませんか?
スクールと違って、周りに仲間が居ない分、感化されたり、インスピレーションを受けたりすることも少ないと思いますので、”情報に飢えている時間”というのが多いはずです。
意識的なインプットって本当に難しいんですよね。
そこで今回は、日常生活の中で無意識にアイデアを収集する事を目的に、映像クリエイターが絶対フォローしておくべきInstagramのアカウントをジャンル別に5つ紹介させて頂きます。
それぞれ一つの分野に特化しているアカウントなので非常に見応えがあります。
良いアイデアというものは、大抵”OFFモード”の時に降りてくるものなので、SNSを流し見している時なんかは最高のタイミングと言えます。
「次はこれを試してみよう!」と思える投稿をどんどん保存して、苦しい思いから解放されましょう^^
独学で映像クリエイターを目指す方にお勧めのインスタアカウント5選

独学で映像クリエイターを目指していると、ついつい何でもかんでも真剣に取り組んでしまいがちかと思いますが、インスピレーションの発信源というのは、殆ど視界の外側にありますので、何気ない時間を有意義に使うのがベストです!
撮影現場の照明テクニック
filmlights
ライティングに特化したアカウントです。
映像制作を行う上でライティングは命です。
何気ないワンシーンにどれだけ照明を使っているかとか、フレームに入りさえしなければ何でもありな照明の立て方などが沢山投稿されていますので、とても勉強になります。
大型の映画撮影の照明は見てて楽しいですし、そこまで大掛かりな事は出来ないにしても、得られる効果は理解できると思うので、制作規模に合わせてアレンジできますね!
作品を印象付けるカラーパレット
colorpalette.cinema
カラーグレーディングがワンパターンになりがちなら是非参考にして下さい。
どの映画作品にも世界観を統一するためのカラリストが入っており、彼らが作ったカラーパレットを基準に作品のカラーグレーディングが行われています。
しかも選ばれた色にはそれぞれ理由がしっかり有り、単に見栄えがどうのとかで済む話では無いので、そのあたりの背景事情なんかを考えながら見る事で、一流のカラリストの背中が見えて来るような気がします。
カラリストに興味のある方はCINEMA 5Dさんのこの記事がオススメです。
カラリストになる方法- Ollie Kenchington氏へのインタビュー
インパクトのある映画のワンシーンをキャプチャー
strangeharbors
この映画と言えばこのシーン!っていうのが絶対ありますよね。
そんな映画の有名なシーンを切り取ったものを大量に投稿しているのがこのアカウント。
どれも緻密な構図で、心に訴えかけて来るものばかりです。
映像を通して伝えたい事をここまで表現出来るってほんと凄いですよね!
積極的にパクるべきだと思います。
構図の解説ををまとめた本もありますが、それのインスタ版ですね。
関連記事
»動画撮影の鉄板カメラアングル12選【心理的な効果を生み出す】
プロの撮影現場の裏側
filmmakersworld
撮影現場の裏側ってめっちゃ勉強になるんですよね
特にアクションシーンのカメラマンなんて、スタントマン顔負けで体張ってますしね。
それ以外にもVFXの制作ビフォーアフターなど「なるほどな!」って思う撮影方法が沢山投稿されています。
僕は主にカメラマンの動線を見たり、周りのスタッフが何やってるのかとかを見て「最小限の人数でやるにはどうしたら良いか?」とか考えてます。
そのワンカットにかける情熱って本当に作品を左右すると思うから、現場のスタッフの方々は本当にプロフェッショナルでカッコいいと思います。
世界中のフォトグラファーやビデオグラファーのカバンの中身
myvideobag
最後はアイデア系ではありませんが
世界中のビデオグラファー/フォトグラファーが持ち歩く機材のレビューを集めたアカウントです。
一人一人個性的で、ドローンだけの人もいれば、スマホだけの人もいるし、レンズがやたら多いとか、それぞれのこだわりが見えて何故か心が和むんですよね。
撮影に明け暮れていると、情熱みたいなものが乾きそうになることもあるんですが、このアカウントを見ていると各々がピュアに撮影を楽しんでいて、彼らも試行錯誤してるんだな~と感慨深い気分になります。
面白いので是非フォローしてみて下さい。
というわけで今回は、映像制作のアイデアが無限に湧き出るオススメのインスタアカウント5選をご紹介しました。
アイデアって、オリジナリティーとイコールではないと思うんですよね。
むしろこの世に完全オリジナルというものは存在しておらず、全てはアイデアとアイデアの組み合わせでしかありませんから、こうやって色んなジャンルの情報に日頃から触れていることが大事です。
既存の制約に囚われ過ぎず、良いところを組み合わせた作品を、世に送り出しましょう^^
では!