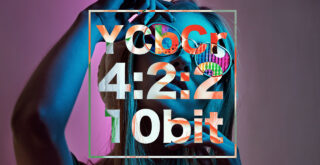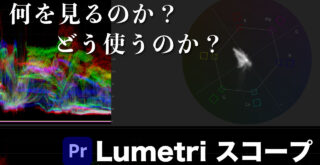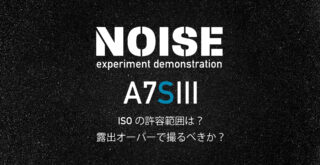ダサい動画の特徴で一番多いのは、固定ショット(フィックス)の質が低いことです。
なので、早い話写真撮影のレベルを上げれば、動画作品のレベルも一気に跳ね上がるということですが、漠然と写真を撮り続けても非効率なので、どういうマインドで取り組めば良いかというお話をしようと思います。
耳にタコかもしれませんが、動画は静止画の連続ですので、フレーム内のバランスやメッセージ性は写真を撮るのと同じでとても重要です。
そして、それを一番顕著に感じるのが固定ショットなのです。
例えばアニメーション業界では、原画マンというポジションがあり、一つのカットの元となる画を描くのが彼らの仕事で、その原画をもとに動画マンが中割りを描いて動きのあるアニメーションを作成します。
業界のキャリアで言うと、動画マンが原画マンを目指すという流れが一般的となっております。
つまり、元となる画はそれほど重要ということで、動きのない固定ショットの場合ごまかしように無いことから、そこでセンスが大きく問われることになるわけです。
そこでオススメなのが、改めて写真を撮りながら学ぶという方法です。
この記事では、センス=経験値と捉え、ビデオグラファーが経験値を爆増させる術としての「写真撮影」の有効性と取り組む上でのマインドに触れていきたいと思います。
脱ダサい動画。写真から学ぶ動画撮影

ダサい動画の原因である固定ショットのレベルの低さは、単純に経験値の問題です。
「カメラワーク」と「カメラアングル」がちょっと曖昧という方はこちらの記事も併せてご覧下さい。
»良いカメラワークとは?基本の10種類を解説【脱ワンパターン!】
»動画撮影の鉄板カメラアングル12選【心理的な効果を生み出す】
ここではRAW撮影を行って、Lightroomで現像するまでの工程を一つの流れとして、それが動画撮影のレベルアップにどう影響を与えるのかを、3つのポイントに絞って解説させて頂きます。
成功体験の数が爆増する
当たり前の話ですが、動画撮影と違って写真撮影は、何パターンも撮れる(撮る)点にあるので、良いショットを叩き出す機会が多くなります。
動画撮影でもしっくりこない場合に何度かトライすることはあると思いますが、写真の比では無いですよね。
加えて、写真は捨てるショットもある程度許容した上でシャッターを切っていくわけですから、設定を少し変えてみたり、レンズを変えてみたりと、色んなバリエーションにトライ出来る為、理想のショットに追い込む事が容易です。
ここで重要なのは、自身の感性を拡張させる機会にどれだけ多く出会えるか?という点です。
その条件下でのカメラの設定やレンズのチョイスも重要ですが、何よりも、自分でこのショットが撮れるという成功体験を、クイックに積み重ねていけるのがポイントです。
改善プロセスの簡略化
感性を伸ばすにあたって、細かすぎるチェック項目は害となります。
ほころびが無い事=良い作品という、面白味のない考え方に染まってしまう危険があるからです。
特に動画の場合、撮影したデータを見比べて「よしこれを採用しよう!」と決めても、後々いろんな問題が発覚して、手詰まりになる事がよくあります。
例えばこんな感じです。
- 再生するとノイズが目立つ
- バンディングが出る
- 一瞬ピントが外れてる
- モデルが変な顔になる瞬間がある
- カメラの揺れが気になる
などなど
その点写真だと、上記の要素とは無縁ですので、それらをクリアしている前提で良し悪しの判断力を養う事ができます。
最終的に上記の問題があれば解決しなければならない事に間違いありませんが、それらは大抵オペレーションミスなので、適切な方法で解決を目指せば良いわけで、それよりも、もっと核に迫る「良いショットかどうか?」という部分にだけ目を向けられる機会を増やす事で感性が磨かれ、成長します。
また、RAWデータの自由度の高さは、どういうショットが正解だったのかを導きやすいという点で、改善ポイントの把握に役立ちます。
大抵は、色温度、露出、ハイライト、シャドウ、構図など簡単なポイントの補正で見栄えが良くなると思うので、後はもっと大切な光の表現や、空気感など、目標としていた事が達成できているかという視点で見る事ができますね。
正解を知り、課題を理解して、再び取り組み、チェックする。
この流れをスムーズに回しやすいのが写真だと思います。
カメラのポテンシャルを知る必要性
一眼レフやミラーレスカメラのポテンシャルは、やはり写真で測れるものだと思います。
使う人の技量も関係しますが、それでも所有するカメラで表現できる最高到達点を探るのには良い方法です。
勿論写真の場合は、画素数の面や、RAW収録という大きなアドバンテージがあるので、単純に動画のクオリティと比較しにくいことは確かですが、自分が使う機材の最大の威力を知っておく事で、動画でどこまで迫る事ができているのかを把握できるわけです。
カメラへの信頼度もアップしますから、例え良い動画撮影が出来なくとも「動画は色々制限されるからな〜」という諦めではなく、「もっといけるはずだ!」という姿勢に変わるはずです。
その時に道標となる最高到達点は、モチベーションを維持する大きな材料となります。
動画撮影のマインドが変わる

写真撮影を多くこなすと、動画撮影時のマインドにも変化が生まれます。
動画撮影の場合、どうしても機材を制御することに意識が囚われがちですが、それが瞬間を狙うことにシフトし始めます。
「撮る」から「獲る」に変わるという事です。
静止画で見ても納得できるかを考え出す
写真撮影を多くこなすと、動画撮影時に「このアングルも一応押さえておこう」なんてザックリした感覚は無くなっているはずです。
動画撮影の場合は、フレーム内の動くものを被写体とし、伝える役目をそれらに全部託してしまう傾向がありますが、それだと、ただ何となく綺麗な映像止まりになるわけです。
しかし、そこに写真的な考え方が入り込む事で、そのワンショットの主題が何なのかが明確になり、そうやって撮られた映像は、失敗のない無難な映像と違って、意味のある瞬間が詰め込まれたものになります。
固定(フィックス)の撮影に強くなる
良い写真が撮れるようになると、フィックス(固定)での撮影に自信がつきます。
そして動画撮影の際、下手に動かすよりもフィックスの方が良いという判断も多くなります。
今まで動くことで動画というアドバンテージに救われていた事を自覚し、固定されたフレーム内で起きる出来事の美しさを楽しめるようになります。
『なんかおもしろい画』を探すようになる
その人の写真のスタイルにもよるのですが、静止画の撮影だけを行ってると、そのうち「画質や構図が綺麗」だけじゃ満足できなくなります。
やはり、そこに小さな物語だったり、連想される物だったり、何かしらのメッセージを放っている1枚を追い求めるようになるんですよね。
これは当然動画にも生きる要素で、動いていようがいまいが、そのワンショットが発する空気感というのは必ずあって、それを嗅ぎ分ける力が養われます。
「撮れるはず」という自信が後押しする
写真で上手く撮れたシチュエーションがあれば、例え動画撮影で同じようなシチュエーションを体験していなくとも「撮れるはずだ」という自信を持って撮影に臨めます。
それが劣悪な環境であればあるほど、写真で到達できたレベルを手掛かりに、画作りを行えます。
写真の場合はそのフットワークの軽さで、カバーできる範囲が広がるという利点と、カメラのポテンシャルを最大に発揮した場合の指標を手に入れることが出来るという利点があるということです。
まとめ

おそらく、動画を撮っている方で写真をやってないという方は、ほとんどいらっしゃらないと思いますが、あえてこのような形で書き綴らせて頂きました。
基本中の基本である「固定ショット」は、写真に取り組む事で経験値を爆増させる事ができるというお話でした。
単純に自己採点できる機会を増やす事で間違いなく成長を助けますし、ダメな写真を撮ってしまった場合は、どれだけ動画のアドバンテージに救われていたのかと反省できますしね(笑)
この記事では、ビデオグラファーの成長において写真撮影が有効である理由についてご紹介いたしましたが、決して写真そのものが簡単だという意味ではなく、そのプロセスからワンショットに込めるマインドを学べるという意味です。
できれば、モデルを使ったり、テーマを決めるなど、本格的な条件下で行うことをお勧めします。
是非積極的に取り組んでみて頂ければと思います^^
ではまた!
こちらの記事もご覧下さい^^
»初心者でも簡単に撮影できるタイムラプスの設定&編集方法