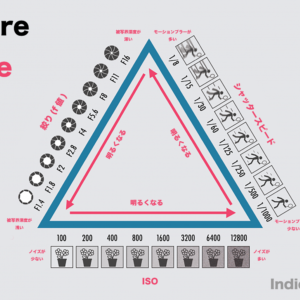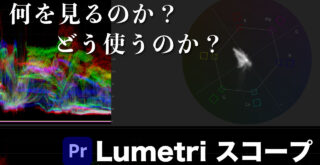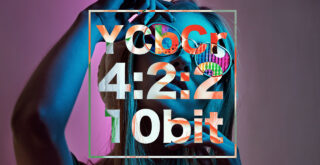動画撮影の際、ホワイトバランスはどの設定(モード)を選ぶべきなのか?
「カスタムホワイトバランスで、毎回グレーカードを使うのか?」
「マニュアル一択なのか?」
「カメラ内蔵のプリセットを使う事があるのだろうか?」
こういった疑問にお答えしていきます。
先に結論を言うと、どれも使います。
と言うのは、そもそもホワイトバランスは、狙い通りならそれで問題ないのですが、撮影環境によってはコロコロ変えなくてはいけないこともありますので、編集のことを考えて出来るだけ一貫性を持たせつつも、現場で最も効率的なオペレーションを心がけると、ケースバイケースになるのです。
では、どういった基準でホワイトバランスの設定(モード)を使い分けているのか、その辺りを詳しく説明していきます。
ホワイトバランスの基礎知識が曖昧という方は、先にこちらの記事をご覧下さい。
»動画撮影のホワイトバランスを理解する【状況に応じた対処法】
動画撮影のホワイトバランス設定と選び方

動画撮影において、基本的にオートホワイトバランスは使わず、固定となります。
理由は、写真と違って時間軸が存在する為、1ショットの中で色を変化させない為です。
とは言え、AWB(オートホワイトバランス)も完全に使わないわけではないので、そのことについても触れたいと思います。
ホワイトバランスを合わせる際に選択する主な設定は以下の4つです。
他にも色々選べますが、基本これだけで事足ります。
- マニュアルホワイトバランス (手動)
- カスタムホワイトバランス
- 太陽光(プリセット)
- オートホワイトバランス(AWB)
上記を、どういった基準で使い分けているのか、その辺りを順番に説明していきます。
マニュアルホワイトバランス(手動)
色温度(ケルビン)を手動で指定して撮影するモードで、一番使う頻度が多いです。
その理由は、目で見た色を再現しやすいという点と、わずかな色の変化に即対応できるからです。
白を真っ白に撮る必要がない場合、例えば白い服にオレンジの光が当たっている時などは、カメラよりも、自分の方が正しく判断できるので、マニュアルが便利です。
あと、編集時にどっちに色を転がすのか決まっている場合などは、撮る段階で完成形に寄せておく方が素材の劣化を防げますので、割と積極的に変えます。
複数代のカメラを使う場合は、色温度を統一するのですが、お互いにズレが出ないように気を付ける必要はあります。
マニュアルホワイトバランスが活躍するシチュエーションは以下の通りです。
- 色温度の変わりやすい環境
- カメラを複数台使う場合
カスタムホワイトバランス
カスタムホワイトバランスとは、グレーカードを使って白の基準をカメラに読み込ませ、自動で色温度をチューニングする機能のことです。
室内で照明を立てて撮影する場合は、色温度が安定している為、よく使います。
グリーンとマゼンタの色被りも補正できるので、撮影段階で完成形に追い込むのには打って付けです。
使用する判断基準としては、色温度が変化しない環境且つ、忠実な色再現が求められるケースです。
「全部忠実じゃなきゃダメなんじゃないの?」って思われるかもしれませんが、マニュアルホワイトバランスの項でもお伝えしたように、夕方のように自然の光の色を忠実に撮る場合もありますので、毎回カスタムホワイトバランスが有効とは限らないのです。
カスタムホワイトバランスが活躍するシチュエーションは以下の通りです。
- 屋内の商品撮影
- 光源が安定しており色温度の変化が無い環境
- 被写体に色被りが多い時
忠実な色再現に関しては、X-Rite ColorCheckerがとても便利で、必ずカメラバッグに入れてます。
詳しくは動画撮影でX-Rite ColorCheckerが使われる理由【機能と使い方を解説】をご参照下さい。
太陽光(プリセット)
屋外で、よく晴れている時はプリセットの「太陽光」で統一してしまうということがよくあります。
大体どのメーカーのカメラでも「太陽光」又は「晴天」が選べるようになっており、マニュアルで5200K(ケルビン)に合わせるのと同じ設定です。
だったらなぜ「太陽光」を使うのか?という話ですが、一番大きな理由は”選択肢”を減らす為です。
昼間の屋外撮影でも、厳密に言えば5200Kだとやや暖か過ぎるので、5500Kにしてみたりなど微調整したくなるところですが、それぐらいの誤差なら編集で調整してもそこまでダメージはないので、撮影に集中する為にも、判断が必要な要素を削っていくということです。

薄雲かかってきたから色温度変更した方が良いかな??

太陽傾いてきたけど、今変えたらまずいかな?どうしようかな?
特にスピード勝負の現場では、ホワイトバランスの他にも色々考えながら撮影をしていますので、少しでも簡略化するというのは重要になってきます。
かと言って全部プリセットを使うわけでもなく、あえて太陽光だけプリセットを使う理由としては、太陽光が他のプリセットと比べて該当する条件がシンプルで、結果に誤差が少ないからです。
「太陽光」が活躍するシチュエーションは以下の通りです。
- 日光が安定している時間帯/環境
- マニュアル操作で値の変更が多く、負担を軽減させたい場合(条件が当てはまれば)
オートホワイトバランス(AWB)
冒頭で、「動画におけるホワイトバランスの基本は固定」とお伝えしましたが、そうもいかず、オートホワイトバランスを使うケースがあります。
「作品」の撮影では使いませんが、「記録」が目的となる撮影では使用することがあります。
特に長時間カメラを回しっぱなしで、その間に色温度が頻繁に変わるシチュエーションでの撮影です。
例えば以下のような撮影があります。
・結婚披露宴
・運動会
・ドキュメンタリー
結婚披露宴の場合、屋内の暖色の照明環境からいきなりカーテンが開いて太陽光になったり、キャンドルだけになったり、とにかく目まぐるしいです。
ドキュメンタリーの場合、屋内から屋外に出たり、明かりが蛍光灯だったり、晴れたり曇ったり、もう手が付けられません。
こういった、やり直しが効かないケースでは、撮れてさえいれば編集で何とか出来る可能性があるので、とにかくカメラを止めずに撮り続けることを最優先に考えてオートホワイトバランス(AWB)を選びます。
ウェディング関係は、慣れている方や、専業でされている方ならAWB以外で撮影されるかもしれませんが、知人に頼まれて初めて撮影する場合はオートホワイトバランスも検討すべきです。
オートホワイトバランスが活躍するシチュエーションは以下の通りです。
- 色温度がよく変わる(読めない)長時間撮影
- 絶対に撮り逃し出来ない場合
* 一点補足ですが、ライブハウスの場合は、上記には該当しますがマニュアルやカスタムで問題ありません。ステージ上の照明が出せる色は決まってますので、白(系)の照明の時に忠実に撮影できるよう設定しておけば基本的にそれ以降変更は不要です。
よく使う4つの設定方法でした!
ホワイトバランス設定の注意点

カメラの性能が良くなっても、人為的なミスがあってはどうしようもありません。。。
ここでは、カメラの性能に便りきって失敗しないよう2つの注意点を挙げさせて頂きます。
- グレーカードの使い方に注意
- RAW撮影での調整
グレーカード使い方に注意
カスタムホワイトバランスを使うときに利用するのがグレーカードです。
グレーカードには色が薄めの50%グレー(ライトグレー)と、色が濃い18%グレー(ミドルグレー)があり、ホワイトバランスを合わせる際は、色が薄めの50%グレーを使います。
色が濃い18%グレーは露出を調整する為にあるものなので、間違って使うと正確なホワイトバランスを得る事が出来ませんので注意しましょう!
(それ以前にカメラによってはエラーになります)
50%って聞くと白と黒の中間のグレーを思い浮かべがちですが、この数値は反射率なので、50%ともなると白に近い色となります。
ちなみに、白いハンカチや、シャツで簡易的にカスタムホワイトバランスを取る方がいらっしゃいますが、中には青みがかった素材などもございますので、「あれ?」と思ったら、無理にカスタムホワイトバランスを使わず、マニュアルで凌いだ方が良いですね。
確実にサンプリングしたい!という方は50%グレーカードを常備しておきましょう。
RAW撮影での調整
RAWで動画を撮影するメリットは、後で自在に色を調整できるところですよね!
なので、RAW撮影時はそこまで慎重にホワイトバランスを合わせる必要がないという事になるのですが、それでもホワイトバランスを合わせる習慣は付けておいた方が良いです。
理由はこの2点です。
- 習慣化する事で、状況から設定を導く力を養える
- 正確なモニタリング環境での撮影は、その場で問題を発見出来る可能性が高い
例えば、規模の大きな撮影の場合だと確認用にREC709環境のモニターを用意するでしょうから、ホワイトバランスの設定を省略することは無いと思います。
しかし、逆に小規模で撮影を行っている場合は、確認作業が少ない分色々と省略しすぎて重大な問題を見逃してしまう可能性が潜んでいますので要注意です。
まとめ

ということで、シチュエーション別に、どのようなホワイトバランスの設定や選び方をしているのかを解説させて頂きました。
基本はマニュアルホワイトバランスが多いですが、撮影環境、撮影内容、優先度によって選び方も変わるという内容でした。
それぞれの設定で得意不得意がありますので、その時の環境に合わせて、カメラが苦手な事を人が補い、カメラの機能を上手く使って人的ミスを最小限に抑えるというのをバランスよくやっていたいですね!
是非試みてください^^
ではまた!